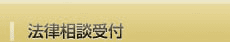第八十八回渋谷法律相談センターコラム「臓器移植について思うこと」
2010年の改正臓器移植法施行により、本人の書面による臓器提供の意思表示があった場合であって、遺族がこれを拒まない場合又は遺族がないときに加え、本人の意思が不明であっても家族の承諾で臓器提供ができるようになりました。また、家族からの書面による承諾により15歳未満の小児からの提供もできるようになりました。報道によると、2023年には、脳死ドナーによる臓器提供が、過去最高の132件、心臓移植が115件行われましたそうです。しかし、厚生労働省の研究チームは、2023年時点で、日本国内で少なくとも1万人の患者が脳死の可能性があると推定しています。今年の5月の時点で、日本では1万6000人以上が移植を待っているとのことですので、臓器移植は、いまだ決して多いとは言えないと思います。
臓器移植の件数が増えない背景の1つとして、日本の臓器移植に関する本人や家族の承諾制度が指摘されています。例えば、スペイン、フランス、イギリスなどの国では、本人が拒否しない限り、臓器提供は自動的に行われるようです。また、アメリカでは、臓器提供の意思表示を義務付ける州が多く、同意する人の割合が高いと言われています。日本人と結婚した知り合いのアメリカ人は、アメリカにいる間に、臓器提供の意思を登録しましたが、日本では、臓器移植に関する家族に対する意思確認が必要であることを知りませんでした。
脳死状態となった患者の家族は、悲しみの中で、臓器移植についての承諾を求められることになりますので、その判断は、容易ではないと思います。後見人として、脳死状態となった本人と接したとき、その目が開き、眼球が動いている様子を見ました。今にも、起き上がりそうでした。ご家族の心痛は、容易に想像できました。
移植のための臓器不足を背景に、この数年、アメリカなどで、遺伝子操作をされたブタなどの臓器を人に移植するという異種移植の臨床研究が、相次いで行われています。日本でも、かかる臨床研究の試みが始まっています。感染症や拒絶反応などの課題は依然として残されているものの、アメリカで、数か月間であったとしても、ブタの腎臓の提供を受けた患者の、透析の苦しみから逃れることができた喜びの声を目にしました。他方で、動物の権利に関する議論もなされています。改めて、臓器移植について、多方面から考える必要があると感じました。